トラブルにならないようにするための宅地建物取引士
不動産取引はとても高額で、一つトラブルが起きると、大きな損害に発展する危険性があります。
専門知識がほとんどないお客さんを、ずさんな契約をしないように、契約前の重要な事項を説明するのが宅建士の仕事の一つです。
だから、宅建士は不動産取引のスペシャリストとも言われているんですね。
宅地建物取引士だけができる3つの業務とは
- 契約締結前に重要事項説明を行う
- 重要事項説明書に記名押印する(宅建業法35条書面)
- 契約書に記名押印する(37条書面)
不動産業者が宅建業者として、仕事をするには、1事務所に5名の従業員に対して、1名以上の宅地建物取引士の設置が義務付けられています。
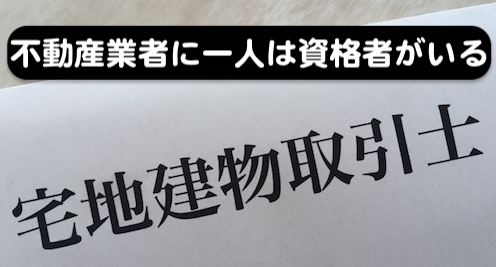
不動産会社で営業マンとして働くだけなら、特に資格はいりません。営業センス次第では、十分な売り上げ数字をあげることも可能です。
営業の世界では、常に営業のカンを磨き続ける接客が重要だからです。
これが、、契約の段階までくると、宅地建物取引士の資格が必要になります。
宅地建物取引業法(宅建業法)では、宅地建物取引士にしかできない3つの業務を定めています。
それが、
- 契約締結前に重要事項説明を行う
- 重要事項説明書に記名押印する(宅建業法35条書面)
- 契約書に記名押印する(37条書面)
です。
契約という法的にも権利が決まりそうだ、という場面では、宅建士の資格が必要なんですね。
不動産という高額な商品を慎重に扱うためでもあります。
営業でお客さんを連れてくるのが、営業マンの仕事で、その後の契約関係は違う人でも構わない、と純粋な営業精神だけを貫くなら、宅地建物取引士の資格はいらないんですね。
この時に、宅建士の資格を持つ営業マンと持っていない営業マンで決定的な違いが出ます。
宅地建物取引士にしかできない業務がある理由
宅地建物取引士にだけしかできない業務って、理由があるんですか?
不動産関係は、苦情や紛争が多いので、重要な点については、資格を持った人が対応することで、信頼をしてもらっているんだよ。
宅地建物取引士にしかできない業務を定めたのは、建前上、不動産のスペシャリスト、というならそれなりの専門家をおきましょう、という面もあるんですね。
宅建業者としての意識に、大きな変化が出て、責任を持つことができるようになるからなんです。
国土交通省が発表したところでは、平成28年度に国土交通省や都道府県で受けた不動産取引に関わる苦情・紛争相談件数は、1734件あったデータがあります。1日5件近くあるわけです。
原因は、「重要事項の説明など」が36%あります。
不動産に関わる法律や法令も改正を繰り返して、実戦ではより高度な専門的な知識も要求されています。
宅建士の資格に登録できない人
新規登録の場合
- 未成年者で、成年者と同一の行為能力がない人(未成年で未婚者の人のこと)
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない人
- 宅建業法違反、傷害罪、暴行罪、背任罪などによって、罰金刑以上の刑を受け、刑の執行から5年を経過していない人
- そのほかの犯罪で、禁錮以上の刑を受け、系の執行が終わり、または執行を受けることが亡くなった日から5年を経過していない人
不動産取引は、平成前のバブル時代などは、いわゆる怖い人が仲介などをしていたこともありました。
そのころは、宅建士の資格も「宅地建物取引主任者」という名前だったんですね。
資格者になれる人が、怖い人だったら不動産取引自体も信用がなくなっちゃいます。
だから、ちょっと厳しめの資格登録要件があるんですね。
宅地建物取引士の資格を持つ人が不動産業者には必ず一人はいる理由とは
不動産関連の資格でも最も知名度の高い資格が「宅地建物取引士」(宅建士)です。
不動産業者が扱う土地や建物、マンションなどは一般的に高額ですよね。
だから、どうしても専門の知識を持った人が、責任を持つことで、買主が満足するようなシステムが必要なわけです。
重要な書類に、宅建士の記名・押印をしてあれば信頼も増し、買主も安心感もあります。
そのために、宅地建物取引士が在籍している、というわけなんですね。
